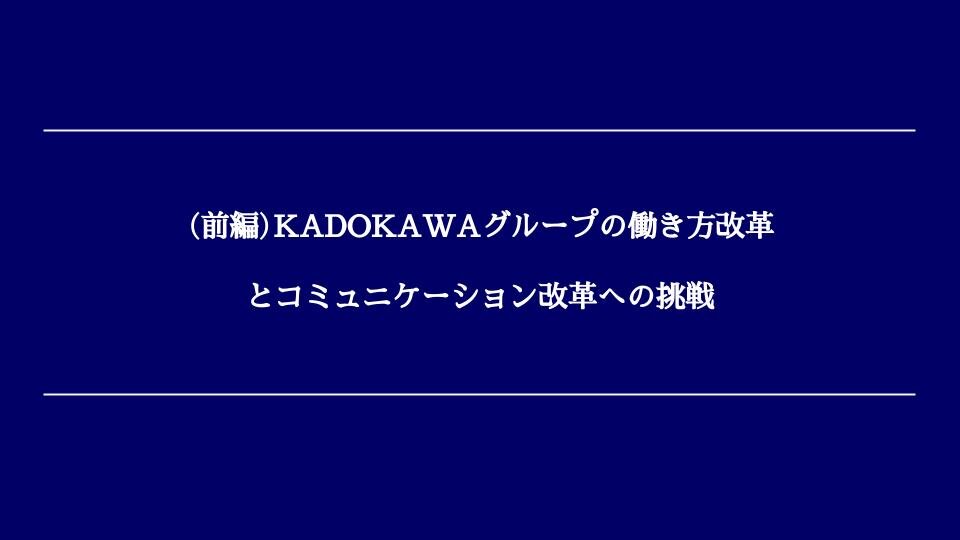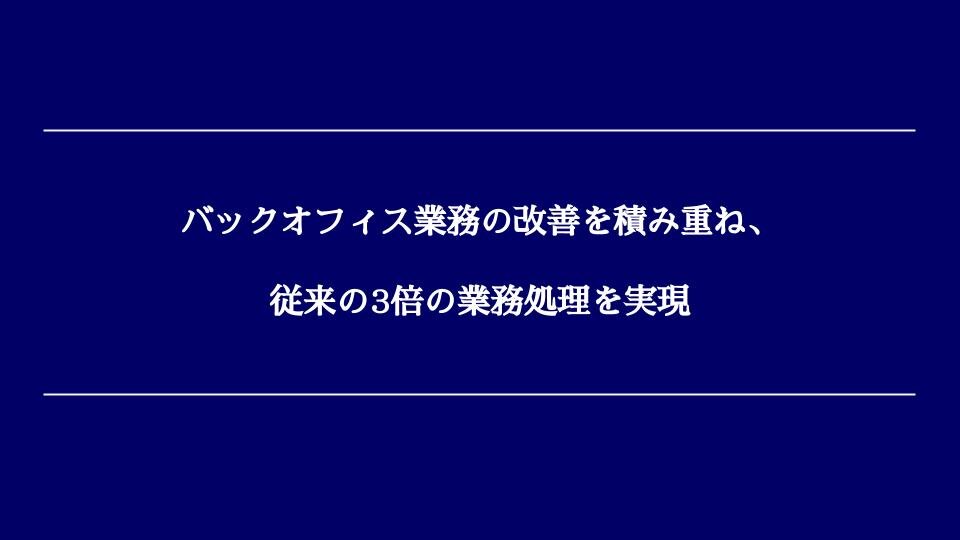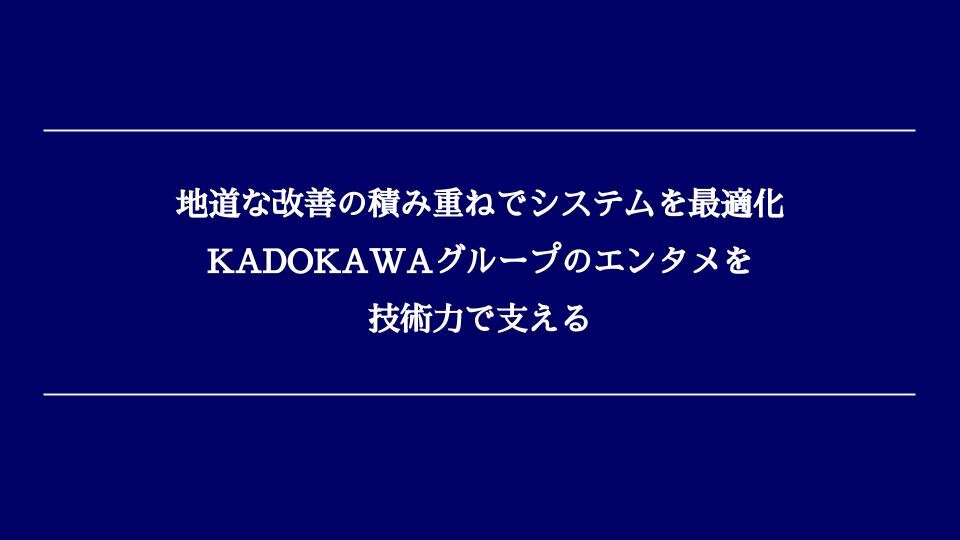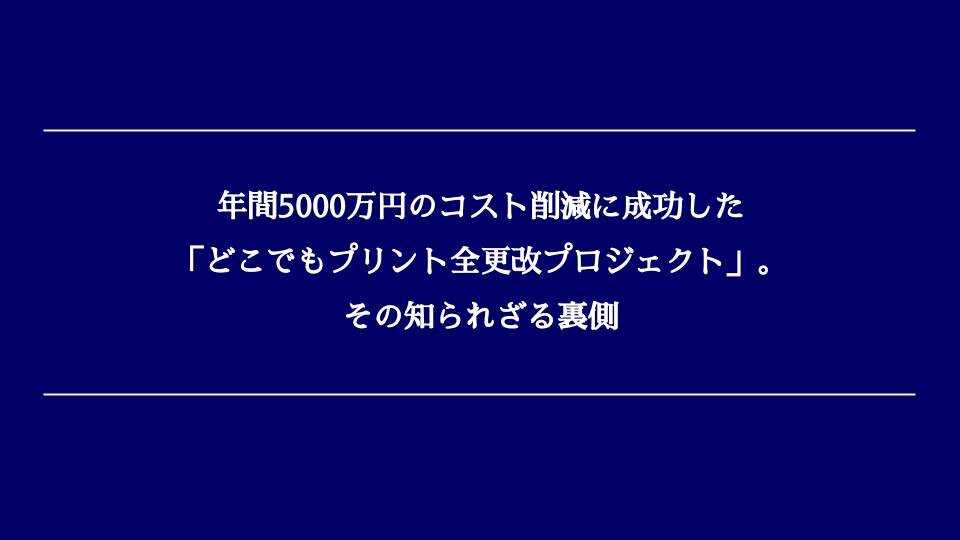働き方改革始動。現場に浸透するまで、施策を何十回と繰り返した
KADOKAWAは総合エンターテインメント企業として、コンテンツを生み出す編集者やプロデューサーらのプロフェッショナル集団だ。それゆえ事業ごとの縦割り文化が色濃く、全社横断での業務改善が進みにくい課題があった。
そこでKADOKAWA ConnectedからKADOKAWAのグループ戦略総務局局長へ働き方改革を一緒に進める提案をし、総務・人事・ICT部門が横串で働き方改革やDXを進めるABW推進チームが発足。渡辺がKADOKAWA Connectedに入社したのは、その直後の2019年9月だった。
渡辺:
入社後すぐにABW推進チームの運営や課題解決に取り組むミッションをいただきました。横串連携が苦手な風土において、組織横断の課題を解決するには現場に深く入り込む必要がありました。私たちは外部コンサルと違ってKADOKAWAグループの社員だからこそ、現場業務にまで踏み込めます。そのためKADOKAWA本社へ出向し、手も足も一緒に動かして現場やキーマンとの信頼関係の構築に注力しました。
当時のKADOKAWAで大きな課題は「コミュニケーションツールの乱立」。全社連絡ひとつとっても、どのツール・媒体を見たらよいのか分からない状態であったと言う。まずはツールを統一し、全員が必要な情報に辿り着ける環境を整えた上で、円滑なコミュニケーションが取れる状態を目指す改善活動が開始された。具体的なツールとして、社内チャットは「Slack」、情報蓄積は企業向けWikiツール「Confluence」を選定。浸透のために、従業員が使うツールを提供するICT部門のEUC(End User Computing)チームとタッグを組んで進めていった。ただ、「ツールが全社へ浸透するまでには、両チームの努力と、数多くの施策が積み重ねられた」と、渡辺が当時を語る。
渡辺:
使い慣れたメールからチャットへコミュニケーション方法が大きく変わるため、最初はなかなかSlackを使ってもらえませんでした。利用者にしてみると、新しいツールは操作を覚える手間がかかるからです。ABW推進チームは、メリットと変える意味を伝えるために全社向けのハンズオントレーニングを続けました。少なくとも2、30回は実施したのではないでしょうか。さらには『出版事業を持つKADOKAWAといえばマンガではないか?』と考え、従業員の目に留まりやすい4コママンガで告知やツール解説をしたり、すぐ使えるTips集を展開したりと、浸透のための施策を試行錯誤しながら進めました。その裏では、複数のツールの統廃合を進め、それに伴って起きるハレーションもひとつずつ片付けていって…。

ABW推進チームは、コミュニケーション改革と並行して、リモートワーク制度にも本格的に着手していく。
渡辺:
KADOKAWAでは、テレワークやリモートワークを“サテライトワーク”と呼んでいます。サテライトワークは人事規程の変更、ICTツールの整備、セキュリティやガバナンスの問題、ITリテラシー向上、自宅とオフィスの在り方まで、幅広い検討が必要です。これらには一貫性のあるルールが求められるため、単一部門で進めるには限界があります。制度検討からガイドラインの作成、社内周知、説明会開催、問合せ窓口の開設とFAQ対応まで、ABW推進チームが組織横断で運用しています。
働き方改革で大切にしたのは、現場の声だ。ABW推進チームが、現場と一緒に進めた施策のひとつに、編集部門向けの「赤入れ用タブレット端末」配布がある。編集者は、作家さんの原稿データを紙出力して赤入れ(文章等の校正で赤字で添削、書き入れすること)を行う。渡辺は、編集者から「毎回大量の出力を行って、それだけでも数十分かかる」「サテライトワークで赤入れをする場合、会社で印刷した大量の紙を持ち歩くのは重く、身体的に辛い」などの声を聞き、タブレットで赤入れができれば紙出力が減って、コスト削減と作業の効率化が実現できるのではと考えた。
ABW推進チームでは編集業務を理解することから始め、アプリやデバイスの選定、業務に即した使い方の定義、PCとタブレットの使い分け、データの受け渡し方法などを検討し、編集現場で試してもらい検証を進めていったのだ。
「この設計なら実運用でも使えそうだ」という目処が立った2020年4月に最初の緊急事態宣言が発令された。幸いにも準備は整っており、どこでも働ける環境を実現するために、即タブレット端末の緊急配布が開始された。図らずもコロナ禍は、編集者が行う赤入れのデジタル化を現場へ浸透させる追い風になったと言う。
渡辺:
編集者は、今まで通りの方法で仕事を進めたかったと思います。けれども出社ができず、藁をも掴む思いで自宅でタブレットを使ってみたら意外と便利だと分かった。そして編集部の他メンバーにも勧める好循環が生まれ、じわじわと浸透して、1年以内には編集者ほぼ全員分、1,000台弱のタブレット端末を配布し終えました。
渡辺は、施策が浸透した要因は2つあったと続ける。
渡辺:
まずはICT部門の目線でツール利用を押し付けるのではなく、現場が抵抗感なくスムーズに使える段取りを組んだことです。もうひとつは、小さな成功体験を積んでもらうことですね。便利だと実感する体験を積み重ねると、あれもチャレンジしてみようと前向きに思ってもらえるからです。
PROFILE
Customer Success部
渡辺 基子 KADOKAWA Connected Customer Success部所属。HPEでテレコム向けSIを担当中、出産・育児の洗礼を受け自身の働き方改革に取り組む。以後、同社にて働き方改革に纏わる技術領域のプリセールス・ビジネス開発を担当。現在はKADOKAWAのコミュニケーション・業務改善活動や、ユーザー視点で事業を変革する組織作りを推進している。