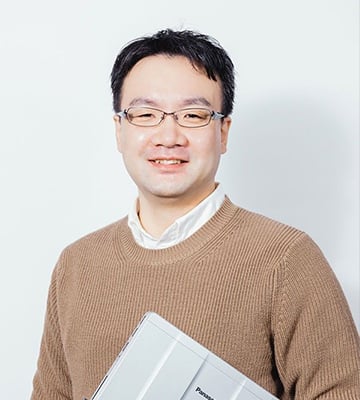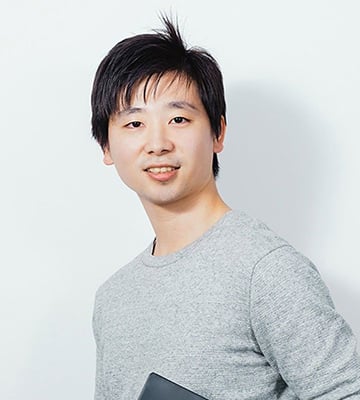親しみのあるエンタメ業界で技術者として成長できると感じた会社
アルゴリズムを研究するために高専から大学に編入
私は高専(高等専門学校)出身で、その頃はよく競技プログラミングの大会に参加していました。競技プログラミングは要件を満たす効率的なアルゴリズムの設計力と、それを時間内に実装しきるプログラミング力が問われる競技です。その中でアルゴリズムの分野に興味をもち、もっと勉強・研究をしたいと思い大学に編入しました。
大学院進学後は組合せ最適化という分野の研究室に入り、効率的な最適化アルゴリズムに関する研究をしていました。
作品作りに技術力で貢献できる会社
学生時代からアニメが好きで、よくCMなどでKADOKAWAの社名も見ており、もともと興味は持っていました。とはいえ分野も大きく異なるので、就活時にKADOKAWAへの応募は考えていませんでした。KADOKAWAの新卒採用特設ページを見たのは完全に興味本位でしたね。そこでKADOKAWA Connectedの存在を知ったのが私にとって大きな出会いでした。
ソフトウェア開発などの技術分野でKADOKAWAグループに貢献できる仕事があるということで興味を持ち、そこからエンジニアリングブログなども読んでこの会社に入りたいという思いを強め、応募を決めました。
参考:KADOKAWA Connected:Engineering Blog
入社の決め手は、成長できる環境があると感じたこと
新卒入社する会社を考える上で、自分がどれだけ学べて成長できる環境なのかは大事なポイントでした。KADOKAWA ConnectedはKADOKAWAとドワンゴのメンバーが集まってできた会社ということで、ドワンゴの技術力の高さは学生時代から耳にしていましたし、エンジニアリングブログを見てもエンジニア精神に力を入れている会社なのだろうと思いましたね。
最終面接前に当時社長だった各務さんの出された本も読んだのですが、外資系やコンサル、SIerなど様々なバックグラウンドを持った社員が集まってできた会社の中で、社員の生産性を最大限まで高めるための方法論が真摯に論じられていました。ロジカルに仕事と会社を分析し、改善しようという精神が感じられ、その点でも信頼できる会社だと思いました。入社後もその印象は変わらず、期待通りの会社だったと感じています。

作品作りを支えるシステム群をよりよくする仕事
入社後、KADOKAWAのメディア事業を支援するシステム開発にジョイン
入社後には2つのプロジェクトに参加しました。1つ目はminael(ミナエル)という社内名称のプロジェクトで、グループ内の情報メディアで扱うイベントのメタ情報(「コト情報」と呼ぶ)を集積・管理し、各メディアに提供するためのサービスです。minaelの機能拡張によるメディア運用業務の負荷軽減や、コト情報の横展開促進といった狙いがあるサービス群となります。
当初アサインされた際のminaelはデプロイが自動化されておらず、私の最初のミッションはCI/CDの導入でした。これにより開発〜本番リリースまでのサイクルを高速化し、ビジネスの変化への適応を早められます。それと同時に、minaelの抱えていた技術的課題の解消のためにコンテナ技術へのインフラ移行も提案し、許可してもらえました。今まで動いていたシステムのインフラ移行を行うのは動作しなくなるリスクも発生するので、慎重にリスク検証を行う必要があります。移行のメリットと想定されるリスクを先輩社員やサービスオーナーに説明しながら進めていくために、打合せを重ねたプロジェクトでした。事前検証は十分に行ったつもりでしたが、実際の移行作業に臨んだ際は検証通りの動作をしないということも多発! その度に焦りながら原因究明と対応を行ったのは大変でしたが、自分の提案で任せてもらった仕事で技術的な学びも大きく、とても充実感を得ながら業務に当たることができました。
書籍出版の裏側を垣間見た費用精算システムの開発
2つ目は、某書籍事業部向けの費用精算システムで、共同制作企業様への請求費用を算出する社内システムです。KADOKAWAではたくさんの作品が生まれていますが、レーベルにより特定の共同制作企業様との協業で作品を生み出している場合があります。そこでは共同制作にかかる費用をパートナー企業と分担するビジネスモデルが採用されています。この実現のために、双方で経費として計上された金額の中から該当する作品群にかかる費用を抽出し、精算額の算出と請求書等の発行を行うのがこの費用精算システムです。
本システムは書籍制作に携わる人たちが本来の作品作りに集中するためのもので、事業の根幹を支える役割を持った、大切な共同制作企業様との信頼関係を繋ぐ大事なシステムです。この仕事を通じて、書籍ができるまでに本当にたくさんの人が関わっていることを感じましたし、出来上がった作品を世の中に届けるために奮闘していることも感じました。対象のレーベル作品を書店で見かけたときには、親しみのような感情を抱いています。
現在はグループを支える基幹システムを改善
現在はKADOKAWAの基幹システムの改善に取り組んでいます。KADOKAWAの基幹システムは、商品となるアイテム管理や、制作費の管理、関わる人員や取引先の情報管理、各種支払管理などが連携したシステム群です。歴史的な背景もあって基幹システムは大規模かつ複雑化しており、それに伴って多くの課題を抱えています。
基幹システム全体の改善を一気に行おうとすると規模が大きすぎるため、着手の容易さとビジネス的な価値などの観点から着手する領域を切り出し、徐々に改善を進める計画が進んでいるのですが、その領域の選定が大変難しいところです。私の所属するチームは領域の選定後に詳細検討や具体化を行うことが多いのですが、検討していくと想定されたよりも影響範囲が大きかったり、各所との調整が必要なことが判明したりして、計画の見直しを余儀なくされることも少なくありません。単純にエンジニアリソースを集中すればうまくいくというプロジェクトでもなく、チームで四苦八苦することも多いです。その中で一部でもシステムアーキテクチャをあるべき姿に変えることができた際には喜ばしく思いますし、謎に包まれたシステムの挙動を明らかにできたときは謎解きのような達成感を覚えることもあります。難易度は高いですが、やりがいのある仕事です。

主体性や挑戦を推奨される環境
空気のようにストレスのないシステム開発を目指す
社内には様々なプロジェクトがありますが、開発チームの風土として共通なのは、各チームに裁量が与えられていて、説明責任を果たせる範囲で技術選定などを自由に行えることです。技術の探究や挑戦は奨励される社風ですし、各チームで自分たちの仕事の仕方を俯瞰し、改善していこうという文化があるので、エンジニアが主体的に働ける会社だと思います。そういった技術的な背景があった上で、KADOKAWAのエンタメという領域に貢献できるのは魅力だと思います。
現在担当する基幹システムは、改善のポイントが多く社内から様々な要望をいただきます。その方々が普段の業務で困らない、空気のようにそこにあってストレスなく業務を進められるような基幹システムを提供できるように、既存のシステムを立て直していきたいと考えています。
主体的な人が輝ける会社
主体的に自分のやるべきことを考えて動ける人は向いていると思います。私たちはグループ子会社ではありますが、親会社のKADOKAWAとの距離は近く、フラットな関係で業務が行えています。そのため、やりたいこと・やった方がいいと考えることを積極的に提案して周囲を巻き込んでいけると、様々なことが実現できると思います。挑戦が推奨される社風というのもあり、様々なことに興味を持って自ら深めていける人は、やりがいの持てる会社ではないかと思います。
Value(行動指針)の中で大切にしたいもの
最も大切にしたいのは「相手を理解する」
私たちはKADOKAWAの要望に応えてシステム開発を行うため、KADOKAWA社員とやりとりをする機会が多くなります。当然ですが、KADOKAWA社員はビジネスについて詳しい方であっても、技術について詳しい方ばかりではありません。そういった方々が抱える本当の課題を見つけ出し、解決策を考え、伝え、共に検討するためには、どう伝えれば相手に理解してもらえるのかしっかり考える必要があります。特に基幹システムの仕事では既存の動いている仕組みに手を入れる場面が多く、それを変えることへの理解を得なくてはいけません。一見うまく動いているように見える仕組みが裏側ではそうでもないことや、この変化が相手にとってもメリットがあるといったことを伝える必要があります。そこでは、相手のことを理解し、相手の立場に立って考えるという意識がとても重要だと考えます。
次に大切にしたいのは「自分への挑戦状を持つ」
古いシステムを改善する仕事をしていますが、今自分たちが開発しているシステムも何年かしたら古くなる、ということは常に意識する必要があると思っています。技術が進化すれば今のシステムも、開発言語も、開発手法もみな古くなるでしょう。
いつの間にか今度は自分たちが改善されるべき対象になっていた、ということがないように、技術の進化に感度高くあり、新しい技術への挑戦に躊躇わない姿勢でいたいと思います。
※2025年2月時点の記事です。