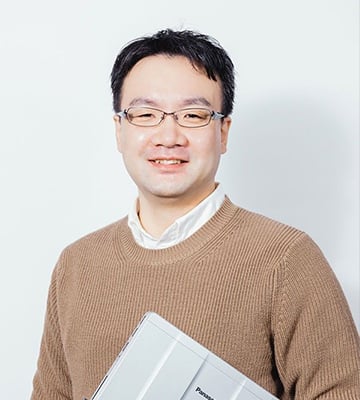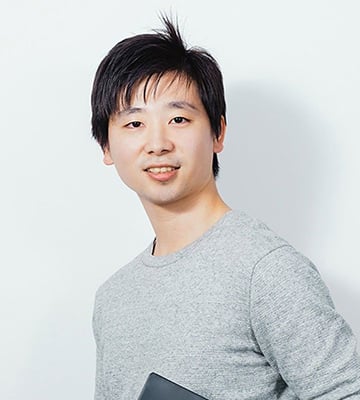自由な発想や気さくなコミュニケーションができる社風の魅力
技術者としての挑戦と、心地よく働ける環境
私は株式会社ドワンゴでデータベース管理の仕事を数年間行ってきました。その後、ニコニコ動画やdwango.jpでインフラ担当として活動しました。時に新規サービスの立ち上げに携わり、プロダクトオーナーの役割も経したこともありました。その後の人事異動で、KADOKAWA Connectedに出向する機会があり、論理系の設定やDC作業などの基本的な業務をはじめ、Ansibleを使用しての構築や自動化の取り組みも経験しました。
私が入社を決めた理由は、出向中にKADOKAWA Connectedの社員と一緒に仕事をし、多くのことを学べたからです。また、自分の場合は上司との距離が近く、1on1で悩みや相談をすることができる環境であると感じました。自由な発想が重視され、先輩や後輩といった枠組みも感じません。気軽に話せる環境が整っていると感じています。

事業部の気持ちに寄り添うインフラエンジニア
最適なソリューション提案が求められるInfraConsulting
私の部署では、KADOKAWAグループの各社に向けてインフラサービスの提供をしています。書籍やアニメ・映画等のWebサイトの依頼を受けることもあれば、新たなWebサービスのインフラアークテクチャの相談を受けることもあります。
私は、InfraConsulting業務を担当しており、グループ各社から要望をヒアリングし、最適な構成の検討や、具体的なインフラサービス提供に向けた情報整理を行います。当社がグループに展開するインフラサービスは多種多様であり、一定の専門知識が必要な仕事です。グループ内には、ドワンゴのような技術に明るい会社もありますが、全てがそうではないため、InfraConsultingチームの出番です。運営している/する予定のサービスがどんなサービスなのか、どんな運用が必要になりそうなのか想定し、最適なプランを提示します。当社では、インフラの環境構築から、インフラ契約の締結、その後の運用支援まで行っているので、顧客に安心して任せてもらえるようなコミュニケーションを心がけています。
責任あるDCファシリティ業務
InfraConsulting業務との関連もあるため、DC(データセンター)ファシリティ業務も担当しています。当社ではKADOKAWAグループ向けにDCの運用をしており、最適な活用ができているかを定期的に確認し、DC内の機器の入れ替えやメンテナンス、時にDCの引越しなどを行います。DC(データセンター)のファシリティ業務は、必要な電力の見積や利用面積の調整など、多少地味に思われる業務もありますが、それが大幅なコスト削減に繋がることも多いのです。DCのコストは巡り巡って、InfraConsulting業務での提供価格にも繋がるので、大切な仕事だと考えています。また、高額なインフラ機器が適切な室内環境で動いているかや、配線が分かりやすくなっているかなど、グループの情報資産を守るための整理整頓も怠りません。DCはKADOKAWAグループの事業成果や知見、利用者の大切な情報が行き交う交差点であり蓄積場所です。その責任感を感じながら業務にあたっています。

KADOKAWAの自由な働き方と協力体制
柔軟なテレワークと、スキル向上のための福利厚生
当社では自由な働き方が奨励されながらも、全員が同じ目標に向かって協力し、ロールアサインリストやROBの仕組みを活用して業務に取り組んでいます。テレワークが主体でありながらも、私は週に3〜4日は歌舞伎座オフィスに出社しており、自宅とオフィスの作業時間を組み合わせることで柔軟に働いています。コロナ禍でコミュニケーションスキルの重要性を実感し、Slackやビデオ会議を通じてリモートワークでのコミュニケーションを図っています。また、新たな分野や技術に挑戦する意欲もあり、現在は、会社から提供される動画学習サービスの「GLOBIS学び放題」を利用して幅広い知識やスキルを習得しようとしています。
Value(行動指針)の中で大切にしたいもの
最も大切にしたいのは「相手を理解する」
InfraConsulting業務において相手を理解することは、なくてはならないスキルでした。お客様のニーズや課題を深く理解し、現場の状況や要件を把握することで、よりよい結果を生み出せると考えています。自分は元々事業部内のインフラ担当をしていましたが、その時の経験が今になって役立っていると感じています。共感したことを相手に伝えると、さらに深い課題感を教えてくれたりし、仲間意識にも似た感情を覚えます。自分はそうした経験をメンバーにも伝え、チームをいい方向に導けるよう努めています。
次に大切にしたいのは「顧客もチームの一員と考える」
顧客を単なる依頼主ではなく、チームの一員として考えることが必要です。お互いが協力し合い、信頼関係を築きながらプロジェクトに取り組むことで、要求された期限に間に合わせることができました。想定外のトラブルが発生してしまう場合も稀にありますが、そのような場合は依頼者もチームの一員として情報共有を行いながら、お互いの作業を確認して解決できるよう取り組んでいます。
※2025年2月時点の記事です。