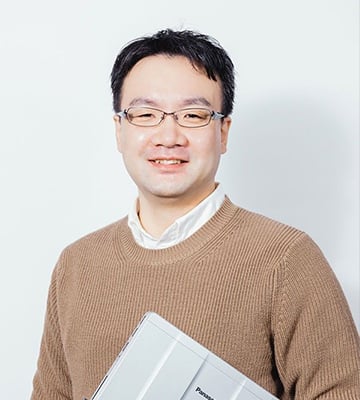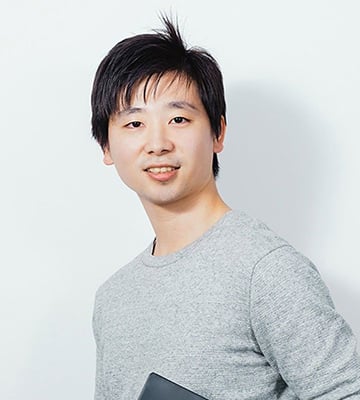深層強化学習にハマった学生時代
大学院でのゲームAI研究
私は、公立はこだて未来大学大学院出身で、システム情報科学研究科知能情報科学を専攻していました。学生の頃はゲームAIをキッカケに深層学習と強化学習を組み合わせた深層強化学習に興味を持っていました。思い出深いのは『LunarLander』のゲームAIで、ロケットをうまく逆噴射して軟着陸させる学習させます。強化学習では上手くできると褒めてあげ、失敗すると叱ることでAIを学習させていくのですが、失敗して硬着陸してしまうと何度も怒られてしまうため、何も考えずに学習させると永遠に着陸せずに中に留まり続けたりします。上手く軟着陸できるような作戦を考えて学習させ、徐々に着陸できるようなっていくのが、人に何かを教えているような感覚があり、楽しくて取り組んでいました。
KADOKAWAへの魅力的な一歩
KADOKAWA作品は昔から好きだったことや、ニコニコなどのサービスで育ってきたこともあり、自分の知っている作品やサービスに関わる事もできるかもしれないと思い応募しました。またデータサイエンティストの視点では、KADOKAWAにはあらゆる作品やサービスに関する膨大なデータがあり、外にいては決して触れられないデータに触れる機会も多いと感じたことも魅力でした。入社後も、その期待が裏切られることはなく、このグループだからこその貴重なデータに日々触れられています。

データサイエンスチームのための仕組みづくりに挑戦
初めての仕事は、機械学習基盤の設計開発
データサイエンスチーム内で利用する、機械学習基盤の設計・構築に携わりました。Amazon SageMakerをベースに、機械学習の実験(PoC)から予測(実運用)まで行うことのできる基盤環境を提供することが私たちのミッションでした。このシステムを利用することで、ハイパワーなマシンの恩恵を受けたり、実行の自動化や監視を行うことができます。
触ったことがなかったAmazon SageMakerの仕様を勉強したり、データサイエンスの知見があるメンバーとして、機械学習周りのユースケースの洗い出しを行い、使いやすい機械学習基盤になるように進めました。自分に想像できていないユースケースがないか調べたり、これまでの経験から想像する必要があり、不安に思いながら設計開発を行っていましたが、無事にリリースすることができました。
自分たちが使うサービスだから貪欲に
現在もこのサービスの開発を担当していますが、自分を含めたチームメンバーが日常的に利用するサービスであるため、使いやすさを大切にし開発しています。ただ、まだ機能的に足りていない部分が非常に多く、満足できていません。不満を感じる挙動があったり、不具合に気づいたらチケットやissueを作成する事でメンバーにも共有したり、改善に着手しやすくしています。今後は、実験のイテレーションを高速化し、効率的に分析・学習・推論・デプロイができるような仕組み化をしていこうと考えています。また、よりよい開発体験のために自動テストやCI/CDが使いやすい環境にしていきたいとも考えています。

キャリアとチームマネジメントへの興味
1on1で認識した興味とキャリア
機械学習基盤の設計・開発に取り組む中で、自然とチーム全体の働きやすさや効率に意識が向くようになりました。上長との1on1でキャリアについて議論を重ねるうち、技術を極めてスタッフエンジニアを目指すよりも、個々人が作業しやすく、チーム全体が効率良く動ける環境づくりや、チームマネジメントに強い興味があると気づきました。入社3年目からは、自分自身がエンジニアとして手を動かす中で発見した課題を、サービスオーナーとしてチーム全体で解消できるよう動くようになりました。これまでキャリアについて深く考えることはほとんどありませんでしたが、入社後に上長との対話を通じて自身のキャリア方針を明確にできたことは重要な事でした。今後も引き続き、チーム全体の業務を最適化する取り組みを続けたいと考えています。
キャリアのための取り組みと上長からのサポート
サービスオーナーとなったことで、コードを書く作業だけに留まらず、ステークホルダーとのコミュニケーション機会が増えました。上長に自分のキャリアに必要な業務や経験を相談したところ、要件の定まった案件でのステークホルダーへの報告だけではなく、ヒアリングや要件定義といったプロジェクト初期段階から関わる機会を積極的に与えてもらえるようになりました。そうした環境の変化の中で、プロジェクトが進行するうちに当初の目的から外れ、手戻りが生じるケースに直面することもありました。そこで、「MLキャンバス」というプロジェクトの目的を常に共有し続ける仕組みを導入し、ステークホルダーと共通の目的意識を保ち続ける取り組みを始めました。現在は、発生した問題への対処が主な業務となっていますが、尊敬する上長や同僚をお手本に、問題を未然に防ぎ、作業者やプロジェクト全体がスムーズに進行できる環境整備に努めていきたいと考えています。
Value(行動指針)の中で大切にしたいもの
大切にしたいのは「自分への挑戦状を持つ」
最近のあるプロジェクトで、データの評価に関する難しい課題に直面しました。数式だけでは解決できない複雑な問題に取り組んでいたところ、チーム全体で新しい技術を活用することで、新たな解決策を見つけることができました。この経験を通じて、挑戦を受け入れることが自己成長への近道であることを実感しました。
※2025年2月時点の記事です。